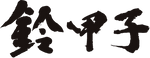天照兜・月読兜の各パーツの特徴や素材をご紹介
はじめに
こちらの記事では、令和7年度の新作である「月と太陽」シリーズの兜本体、

1/5スケール 天照(てんしょう)兜 と 1/5スケール 月読(つきよみ)兜の各パーツの名称や素材について細かくご紹介していきます。
天照は太陽を、月読は月をイメージした兜となっております。
各部位のご紹介
兜鉢(かぶとばち)
兜鉢には合わせ鉢という技法を用いており、正式名称を「剥(は)ぎ合わせ鉢」といい、複数の鉄板を剥ぎ(はぎ)と呼ばれるパーツに分けて作り、それらをつなぎ合わせることで一つの兜の形を作る技法のことです。
兜は、頭部を保護するために丈夫な構造が求められますが、一枚の鉄板を成形することは難しく、重くなりすぎるという問題があります。そこで、昔の職人たちは鉄板を複数の小さなパーツに分け、それを一つに組み合わせることで軽量かつ丈夫な兜を作り上げました。

天照と月読は、鉄板にアルミを加工した鋲(星といいます)を打つ、古来の技法を再現しています。
兜鉢の正面と後ろには「月と太陽シリーズ」専用の錫金具を使用しております。天照は太陽の光を、月読は 月とウサギをデザインしました。
| 素材 | 鉄、アルミ、錫 |
鍬形(くわがた)
鍬形(くわがた)とは、兜に付けられる装飾の一部のことです。
兜の前面に取り付けられる二本の角のような形状をした部分を指します。
兜全体のデザインの中でも非常に目立つ部分で、元は装飾としての意味合いが強かったのですが、徐々に武士の身分や個性を象徴する重要な飾りとなっていきます。

天照についている鍬形は、大鍬形という太い鍬形で鳥毛の模様を表面に打ったものです。
月読についている鍬形は、月をイメージした シャープな形状の鍬形です。表面は、ヘアライン加工(金属を研磨し髪の毛ほど細い線を全面に施す)で仕上げております。
|
素材 |
真鍮に24K鍍金 |
錣(しころ)
錣(しころ)とは、兜の後ろや側面に付いている部分で、首や肩を保護するための重要なパーツです。兜の頭部だけでなく、首元から肩のあたりまでをカバーすることで、敵の攻撃や矢から武将の体を守る役割を果たしていました。
穴の空いた金属の板に、糸を通す威という技法を使っており、糸の色や模様によって兜の印象が作られていきます。

天照は真朱と呼ばれるレンガ色の威と白の威で 太陽と雲を表現し、月読はグレーとブルーを威し、月の淡い光を表現しました。
|
素材 |
アルミ、正絹糸 |
吹き返し(ふきかえし)
吹き返し(ふきかえし)は、兜の前部や側面に取り付けられた、外側に折り返したような形をした部分です。
この部分は、兜のデザインの中でも特に目立つ箇所で、装飾的な役割と防御的な役割の両方を持っています。

天照と月読は、菊の花柄の皮を使用し、その上に透かしの丸い錫金具と花の真鍮金具を取り付けております。華やかさと重厚感を演出しました。
| 素材 | 合皮、錫、真鍮 |
忍緒(しのびのお)

| 素材 | 人絹 |
付属品について
作家札

鈴甲子雄山の作品である証となる 作家札です。コンパクトで安定感のある、プレート付きの札です。
| 素材 | 天然木・真鍮 |
袱紗(ふくさ)
布地を表裏二枚合わせ、または一枚物で、ふろしきより小さい方形に作ったものを袱紗(ふくさ)と言います。
進物に掛けたり、茶道で茶碗を受けたりするためにも使われており、礼儀を尽くす際に用いられています。

天照と月読には、グレーとベージュの中間色であるグレージュ色の袱紗が付属します。
| 素材 | 人絹 |