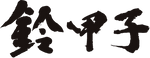竹雀兜の各パーツの特徴や素材をご紹介
はじめに
こちらの記事では、奈良県の春日大社に奉納されている、国宝の赤糸威鎧(竹虎雀飾)の兜を模写した、「竹雀兜(たけすずめかぶと)」の各パーツの名称や素材について細かくご紹介していきます。
竹雀兜はサイズの大きい順に、1/3スケール、1/4スケール、1/5スケールの三種類で製造しております。

こちらの記事では「1/4スケール 竹雀兜」でご紹介していきます。
各部位のご紹介
兜鉢(かぶとばち)
兜鉢には合わせ鉢という技法を用いており、竹雀兜では、鉢の筋に覆輪(ふくりん)という金の帯を巻いています。
合わせ鉢は正式名称を「剥(は)ぎ合わせ鉢」といい、複数の鉄板を剥ぎ(はぎ)と呼ばれるパーツに分けて作り、それらをつなぎ合わせることで一つの兜の形を作る技法のことです。
兜は、頭部を保護するために丈夫な構造が求められますが、一枚の鉄板を成形することは難しく、重くなりすぎるという問題があります。そこで、昔の職人たちは鉄板を複数の小さなパーツに分け、それを一つに組み合わせることで軽量かつ丈夫な兜を作り上げました。

竹雀兜では鉄板に、アルミを加工した鋲(星といいます)を打つことで、古来の技法を再現しています。また、実物の兜と同じく、八幡座(はちまんざ)という穴の開いた天辺の金具から、六方向に広がるように金具が配置されている「六方白」という形状の兜鉢です。
八幡座・六方白の金具はともに、竹と雀を彫金して鋳造した錫(スズ)で出来ております。竹雀兜は、こうした竹と雀の金具を兜全体に配しているのが特徴です。
| 素材 | 鉄、アルミ、錫 |
鍬形(くわがた)
鍬形(くわがた)とは、兜(かぶと)に付けられる装飾の一部のことです。
兜の前面に取り付けられる二本の角のような形状をした部分を指します。
兜全体のデザインの中でも非常に目立つ部分で、元は装飾としての意味合いが強かったのですが、徐々に武士の身分や個性を象徴する重要な飾りとなっていきます。

竹雀兜についている鍬形は大鍬形(おおくわがた)という種類で、横に大きく広がった存在感のある形となっています。
| 素材 | 真鍮に24K鍍金 |
錣(しころ)
錣(しころ)とは、兜(かぶと)の後ろや側面に付いている部分で、首や肩を保護するための重要なパーツです。兜の頭部だけでなく、首元から肩のあたりまでをカバーすることで、敵の攻撃や矢から武将の体を守る役割を果たしていました。
穴の空いた金属の板に、糸を通す威(おどし)という技法を使っており、糸の色や模様によって兜の印象が作られていきます。

竹雀兜は朱赤色の威を編んでおります。裾には錫金具が付きます。
| 素材 | アルミ、正絹糸、錫 |
吹き返し(ふきかえし)
吹き返し(ふきかえし)は、兜(かぶと)の前部や側面に取り付けられた、外側に折り返したような形をした部分です。
この部分は、兜のデザインの中でも特に目立つ箇所で、装飾的な役割と防御的な役割の両方を持っています。
 竹雀兜は実物の皮を元にデザインした獅子の絵皮を使用し、その上に、吹き返しのカーブに沿った錫金具を鋲で留めております。
竹雀兜は実物の皮を元にデザインした獅子の絵皮を使用し、その上に、吹き返しのカーブに沿った錫金具を鋲で留めております。
| 素材 | 豚皮、錫 |
忍緒(しのびのお)

| 素材 | 人絹 |
付属品について
作家札

鈴甲子雄山の作品である証となる、作家札です。
| 素材 | 天然木 |
袱紗(ふくさ)
布地を表裏二枚合わせ、または一枚物で、ふろしきより小さい方形に作ったものを袱紗(ふくさ)と言います。
進物に掛けたり、茶道で茶碗を受けたりするためにも使われており、礼儀を尽くす際に用いられています。

1/4スケールの竹雀兜には、紫色の袱紗が付属します。
| 素材 | 人絹 |
芯木(しんぎ)
芯木は兜を支える木製の土台のことです。

1/4スケールの竹雀兜にはお櫃と同じ黒の天然木で作った、猪目(いのめ)と呼ばれる模様のついた芯木が付属します。
猪目は猪(イノシシ)の目を意味するハートのような形で、猪のように勇敢に立ち向かうことを願って付けられた、日本古来の文様です。
| 素材 | 天然木 |
お櫃(おひつ)
竹雀兜には、収納のためのお櫃が標準でついております。
お櫃は、兜やその他の飾り物を安全に収納するための箱です。使用しないときは、しっかりと収納することで、埃や汚れから守ることができます。これにより、飾り物の劣化を防ぎ、長持ちさせることができます。
また、防湿の観点からもお櫃は足で箱を持ち上げている構造のため、湿気を下に逃す構造になっています。金属や絹糸は多湿の環境における劣化が早いので、お櫃で収納することをおすすめしております。

1/4スケールの竹雀兜には天然木を黒塗装したお櫃が付属します。
| 素材 | 天然木 |